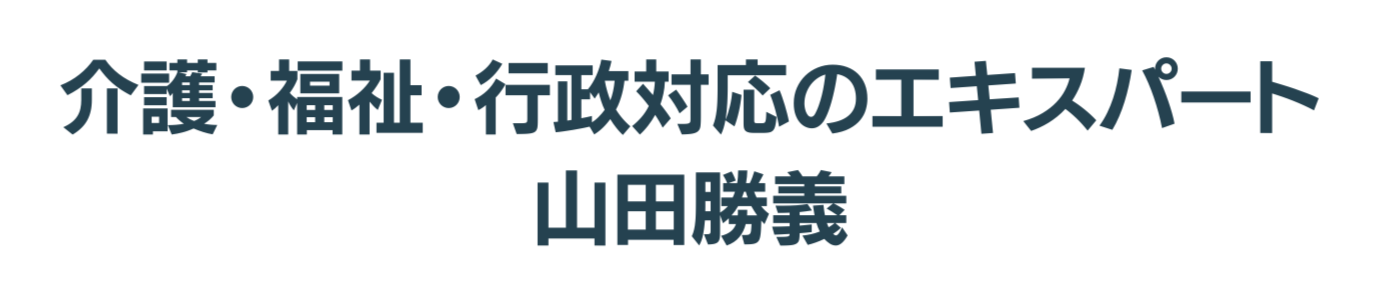前回のブログ「監査等に引っかかった場合の返戻手続きや介護報酬の計算方法を理解していますか」では、前半部分で「介護報酬を算定するにあたっての端数処理」を示しました。
これは前回も申し上げたとおり、現在、各事業者は、令和6年度介護報酬改定において様々な改定準備に着手していると思います。例えば、重要事項説明書や介護報酬改定に伴う顧客宛ての同意書等、こういった部分では新たな介護報酬改定の状況を示し、利用者に説明・同意をする場面が出てくると思います。
利用者からすると、介護保険を利用するにあたり「自分の負担がどの程度増えるのか?」、この部分は一番興味がある部分です。
そして、そして介護保険事業者は利用者に対し「概ねの概数」による介護保険の増加額を利用者にお伝えすることとなると思いますが、ここで皆さんは介護報酬の単位数(基本報酬・加算部分)の求め方、特に介護保険の単位数・金額の「端数処理」、つまり介護報酬金額の求め方や端数処理を理解していますか?
「私は介護報酬を算定するソフトに入力するから知らない。」などという言い訳は、利用者には通じません。このようなことを言っていたのであれば、利用者やご家族の信頼を一気に失うことでしょう。
そういった意味で、今回は、介護報酬を算定するにあたっての「端数処理」を具体的に「計算例」を用いて説明を行ってみますので、しっかりと確認をお願いいたします。
介護報酬(単位数・金額)の計算方法、端数処理の原則
冒頭、介護報酬の計算方法で、大きな基本的な考え方をお伝えします。こうすれば、介護報酬の単位数の算定、金額の算定にあたって、大きな間違いはないはずです。時間の無い方は、この部分・原則を理解できれは良いです。
⇒この原則をしっかりと確認しましょう。分かっていれば良いですし、分かっていないのであれば、しっかりと覚えましょう。
★介護報酬の単位数の算定の端数処理・・・1単位未満の端数は「四捨五入」
★介護報酬の金額を求める場合の端数処理・・・1円未満の端数は「切り捨て」
では、次に具体的な介護報酬(単位数・金額)の具体的な計算方法の説明に移ります。
介護報酬(単位数)の具体的な計算方法、端数処理
まず、介護報酬は、それぞれの介護サービス毎における介護報酬の「単位数」が示されています。この単位数をもとに以下、算定します。
介護サービスにおける介護報酬には基本報酬部分が存在します。これに「加算部分」、「減算部分」が設定されています。この基本報酬部分と加算部分・減算部分を加えてから端数処理をします。
この場合の介護報酬の単位数を求める場合、小数点以下の端数処理は、「四捨五入」です。数式ですと以下のとおりとなります。
【介護報酬の単位数を求める場合の端数処理】
(例)午前6時(早朝)に訪問介護を30分未満行った場合
訪問介護(20分以上30分未満)250単位+早朝の割増25/100 =312.5単位
⇒この場合1単位未満、つまり小数点以下の端数「0.5円」は「四捨五入」を行い、「313単位」となります。・・・①
介護報酬の単位数を求める計算過程において、小数点以下の端数が生じた場合、小数点以下の端数を都度、「四捨五入」として計算を行い、絶えず「整数値」に割合を乗じ、計算を行うという手続きを行います。
よって上記の場合は、小数点以下の端数「0.5単位」が生じていることから、四捨五入を行い「313単位」となるということです。
介護報酬(金額)の具体的な計算方法、端数処理
上記、「①介護報酬の単位数を求める場合の端数処理」を求めた後、次に介護サービス種類・地域区分に応じた「1単位あたりの単価」を乗じて介護報酬の全体の金額(介護保険負担金額+自己負担金額)を求めます。
【介護報酬の全体の金額を求める場合の端数処理】
(例)この介護サービス事業所の所在地域は「横浜市」とし、介護サービス類型は「訪問介護」、地域単価は「11.12円」として算定します。
313単位(①)×11.12円 =3,480.56円
⇒この場合1円未満の端数「0.56円」は「切り捨て」を行い、「3,480円」となります。・・・②
介護報酬における介護保険負担金額の計算方法、端数処理
前項までで、介護報酬の全体の金額は求められたわけですが、この介護報酬の全体の金額には、前述のとおり「介護保険負担金額」と「自己負担金額」が存在しますので、この項では、「介護保険負担金額」の部分の求め方を確認します。
【介護保険負担金額を求める場合の端数処理】
3,480円(②)×0.9(介護保険金額:自己負担金額が1割負担の場合) =3,132円・・・③
3,480円(②)×0.8(介護保険金額:自己負担金額が2割負担の場合) =2,784円・・・③
3,480円(②)×0.7(介護保険金額:自己負担金額が3割負担の場合) =2,436円・・・③
⇒この場合、1円未満の端数が生じた場合は「切り捨て」を行います。
⇒上記、計算例では1円未満の端数は生じず、「全て1円単位」として算定されてしまいました。すみません。笑
ここで何よりも注意すべきは、「介護保険負担金額」を「自己負担金額」よりも先に算定するということです。
介護報酬における自己負担金額の計算方法、端数処理
手順としては、最後に介護報酬における自己負担金額を求めることになります。以下にその計算方法と端数処理を示します。
【自己負担金額を求める場合の端数処理】
3,480円(②)-3,132円(③)(自己負担金額が1割負担の場合) =348円
3,480円(②)-2,784円(③)(自己負担金額が2割負担の場合) =696円
3,480円(②)-2,436円(③)(自己負担金額が3割負担の場合) =1,044円
⇒この場合、1円未満の端数が生じた場合は「切り捨て」を行います。しかし、介護保険金額を計算した時点で、すでに整数値となっていますので、「端数処理は無い」はずです。
介護報酬を求めるにあたって端数処理の手順をまとめる
前項まで、具体的な介護報酬の計算方法、そして端数処理を説明してきました。本項では、介護報酬を求めるにあたっての端数処理を「手順を追った形」でまとめます。
①介護報酬の単位数を求める場合の端数処理・・・1単位未満の端数は「四捨五入」
↓
②介護報酬の全体の金額を求める場合の端数処理・・・1円未満の端数は「切り捨て」
↓
③介護保険負担金額を求める場合の端数処理・・・1円未満の端数は「切り捨て」
↓
④自己負担金額を求める場合の端数処理・・・1円未満の端数は「切り捨て」
⇒ただし、上記③の時点で、すでに整数値なので「端数処理無し」。
大切なのは、これらの端数処理の手順を、上記①~④に沿った形で行わないと、それぞれの時点における「金額に差異」が生じますので注意が必要です。
まとめ
今回は、介護保険事業を行ううえで、具体的な介護報酬の求め方、そして端数処理という介護保険にかかる「お金の処理方法」について、ブログを書いてみました。
このブログをお読みになられた事業者の方は、介護ソフト頼りではなく、是非ご自分の手で介護報酬を求める手順を確認しておくことをお勧めします。
なぜならば、介護保険を利用する利用者や家族にとって、介護報酬改定があった場合、
「利用者の介護保険の負担金額がどのくらい増えるのか」
ということは、非常に大きな興味がある部分であることは間違いないはずです。
よって、介護保険を利用者からすると、介護保険を生業とする事業者が、介護報酬の計算方法や端数処理の求め方も分からないということであれば、当然信頼など得ることはできません。
今回のブログをお読みいただき、誠にありがとうございました。次回のブログもお楽しみに。