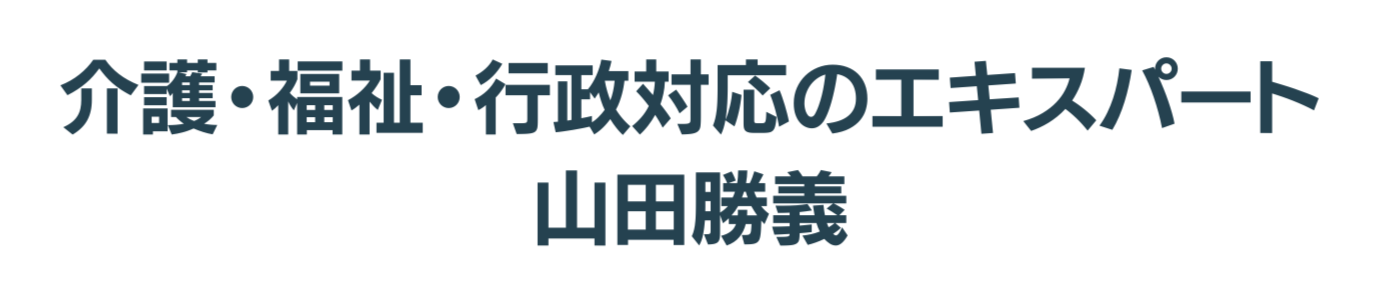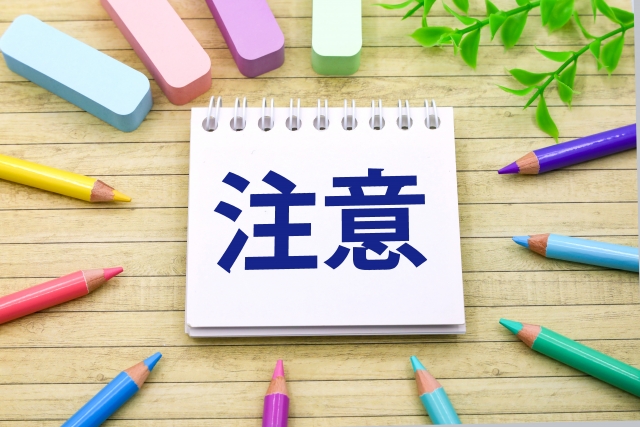皆さん、こんにちは。元有料老人ホームの施設長を担当していた税理士・行政書士の山田勝義です。
さて、今回のブログでは「要注意です「身体拘束廃止未実施減算」に対する対応ができていますか?」という題名でブログを書きたいと思います。
ご存じのとおり、利用者に対する高齢者虐待防止に関する取組みとしては、令和6年度介護報酬改定として介護事業のほとんどの類型には、「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用開始されています。
これに先立ち、身体拘束防止に関する取組みについては、平成30年度介護報酬改定より身体的拘束等の適正化のための指針の整備や身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期開催が義務づけられています。
つい、事業者としては、虐待防止に関する取組みに注力してしまうと、つい身体拘束防止に関する取組みが甘くなってしまう可能性があるのではないでしょうか。
こうしたことを受け、この度、私のブログでは「身体的拘束適正化委員会」というカテゴリーを新たに設け、このカテゴリーでは事業所における身体拘束防止に関する取組みや身体拘束防止に関する取組みについても継続的に記載していこうと思います。
では、早速ですが、事業所として確認しなければならない事項を、次項以下に書きますので、しっかり確認をお願いします。
また、ブログの末尾に「身体的拘束適正化委員会」の議事録のひな形を付けておきますので、ぜひご利用ください(この議事録を無料ダウンロードできるようにしておきます)。
安易に「身体拘束」を考えていないですか?(身体拘束は原則「禁止」)
老後生活の最大の不安である介護を社会全体で支え、高齢者の自立を支援することを目的とした介護保険制度は平成12年4月にスタートしました。それに伴い高齢者が利用する介護保険施設等では身体拘束が禁止され、介護の現場では、「身体拘束ゼロ作戦」として身体拘束のないケアの実現に向け、様々な取り組みが進められています。
☞身体拘束ゼロの時代へ (平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)
この身体拘束は、人権擁護の観点から問題があるだけでなく、高齢者のQOL(生活の質)を根本から損なう危険性を有しています。そして身体拘束は、高齢者の身体機能は低下し、寝たきりにつながる恐れもあり、また、人間としての尊厳も損なわれ、時には死期を早めるケースも生じかねないのです。
ゆえに身体拘束の問題は、高齢者ケアの基本的なあり方に関わるものであり、関係者が一致協力して身体拘束を廃止しようとする取り組みは、我が国の高齢者ケアの転換を象徴する画期的な出来事であると言えるものです。
身体拘束は、緊急やむを得ない場合、つまり要件として「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合、「身体拘束等の適正化のための指針」に従い、はじめて利用者に対し、身体拘束を実施することができるということなのです。
本当に身体拘束は「やむを得ない」ものなのだろうか?
従前より、患者や利用者に対する身体拘束は、医療や看護の現場では、援助技術の一つとして、手術後の患者や知的能力に障害がある患者の治療において、安全を確保する観点 からやむを得ないものとして行われてきた実態があります。
また、高齢者施設等においても、その影響を受ける形で、高齢者の転倒・転落防止などを理由に身体拘束が行われてきました。こうした身体拘束に対する「安易な考え方」から現場職員は、患者や利用者に対する身体拘束の弊害を認識しながらも廃止できないジレンマ、そして患者や利用者を「縛らなければ安全を確保できない」というような考えを持つに至り、結果として、身体拘束への抵抗感を次第に低下させているのでないでしょうか。
こうしたことから、実態として高齢者施設等で、実は「緊急やむを得ない場合」として身体拘束を行っているケースは少なく、むしろ身体拘束に代わる方法を十分に検討することなく、「やむを得ない」と安易に身体拘束を行っているケースも多いのではないのではないでしょうか。
確かに、身体拘束を行う理由には、家族が施設や病院側の説明を聞き、これに対する「家族の同意があるから許される」という考え方もあるでしょう。
しかしながら、この同意を行った家族にとっては「他に方法のないやむを得ない選択であったこと」、「縛られている親や配偶者を見て」、苦悩し、そして後悔している気持ちを受け止めなければならないのです。
また、身体拘束が廃止できない理由として、「スタッフの人数不足」をあげる意見もあります。確かに、明らかな人員不足は解消しなければならないのですが、実態として現行の人員体制で、様々な工夫をしながら身体拘束を廃止している病院や施設もある反面、それを上回る人員体制でありながらも患者や利用者に対し、身体拘束をしている病院や施設も存在しているのです。
こうしたことから、本当に身体拘束が「やむを得ない」ものなのかを、手順を含め、しっかりと検討することが非常に重要なのです。
身体拘束を行うことはなぜ問題なのか?
患者や利用者に対して、身体拘束を行うことは良くない(原則、禁止されている)のは理解できたとします。では次に患者や利用者に対して、身体拘束を行うことはなぜ問題なのかについて、具体的に確認したいと思います。
この患者や利用者に対する身体拘束がもたらす弊害には、次のとおり「身体的弊害」と「精神的弊害」があります。
①身体的弊害
ア 身体拘束は、利用者本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生などの外的弊害
イ 身体拘束は、食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害
ウ 車いす等に拘束した場合、利用者が無理な立ち上がりにより転倒事故が発生、またベッド柵を使用した場合、利用者が柵を乗り越えてしまうことによる転落事故、さらには抑制器具による窒息等の大事故を発生の危険性
②精神的弊害
ア 本人に不安や怒り、屈辱、諦め等、大きな精神的苦痛を与え、そして人間としての尊厳の毀損
イ 身体拘束によって、認知症状がさらに進行し、せん妄の頻発をもたらす恐れ
ウ 本人の家族にも大きな精神的苦痛を与える。また、自らの親や配偶者が拘束されている姿を見たとき、後悔し、そして罪悪感にさいなまされる家族
エ 職員も自らが行うケアに対して誇りを持てなくなり、安易な身体拘束は士気の低下を招く
患者や利用者に対する身体拘束は、「身体的弊害」「精神的弊害」というような弊害をもたらし、結果として安易な身体拘束は、本来のケアにおいて追求されるべき「高齢者の機能回復」という目標とまさに正反対の結果を招く恐れがあるのです。
身体拘束の具体的な行為を確認しよう
患者や利用者に対して、身体拘束を行うことは良くない(原則、禁止されている)のは理解できたとします。では、患者や利用者に対する身体拘束の行為(具体例)を理解できているでしょうか。
ここでは、介護保険指定基準において 禁止の対象となる身体拘束の具体的な行為の例(ア~サ)を確認したいと思います。
ア 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
イ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
ウ 自分で降りられないように、ベッドを棚(サイドレール)で囲む
エ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
オ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
カ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
キ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
ク 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
ケ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
コ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
サ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
身体拘束を行ううえでの慎重な手続きの運用・手順きについて
身体拘束を行うには以下の手続きが必要となります。
身体拘束は、緊急やむを得ない場合、つまり要件として「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合、「身体拘束等の適正化のための指針」に従い、はじめて利用者に対し、身体拘束を実施することができる
事業者が身体拘束を行うため、上記の手続きを具体的に行う手続き等は以下のとおりとなります。
①緊急やむを得ない場合に該当した場合の手続
緊急やむを得ない場合に該当するか否かは、組織全体として判断が行われるよう、以下の手続を定めます。
ア 身体拘束廃止委員会により協議
イ 3つの要件(切迫性、非代替性、一時性)に合致しているか
ウ 関係者が幅広く参加すること
②利用者等本人および家族への詳細な説明、理解を得るべき内容
ア 身体拘束の内容、目的、理由
イ 身体拘束の時間、時間帯、期間
ウ 施設長等の責任者からの個別説明
③身体拘束を行う要件を常に検討する必要性
ア 身体拘束されている入居者の観察
イ 緊急やむを得ない場合が継続しているのかを検討
ウ 緊急やむを得ない場合に該当しなくなった場合には直ちに解除
身体拘束の「緊急やむを得ない場合」とは?(3つの要件)
患者や利用者に身体拘束を行う場合、その判断基準として「緊急やむを得ない場合」として、「3要件に合致していること」が必要となります。
この3要件とは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」であり、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合に、患者や利用者に対し身体拘束が行われることとなる。つまり、この3要件が外観上、満たされるからとして、安直に患者や利用者に身体拘束を行うことは、厳に戒めなければなりません。
ここでは、身体拘束をやむを得ず行う場合の3要件を確認します。
①切迫性
「切迫性」の判断を行う場合、身体拘束を行うことにより、本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、入居者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。
②非代替性
「非代替性」の判断を行う場合、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずに介護する全ての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要があります。
また、身体拘束の方法自体も、入居者本人の状態に応じ、最も制限の少ない方法により、行われなければなりません。
③一時性
「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態に応じ、最も短い拘束時間を想定する必要があります。
「身体拘束廃止未実施減算」とは
すでに「身体拘束廃止未実施減算」については、平成30年介護報酬改定から適用されています。そして、 事業所として身体的拘束等が行われていた場合ではなく、居宅サービス基準の記録(身体拘束等を行う場合の記録)をはじめ、所定の措置を講じていない場合、利用者全員について所定単位数から減算されることになります。
具体的には、以下の事項を実施していない場合「身体拘束廃止未実施減算」の適用を受けることになります。
★事業所として行わなければならないこと。
① 身体拘束を行うための記録を行うこと
② 身体拘束等適正化検討委員会を開催すること(3月に1回)
③ 身体拘束等の適正化のための指針の整備
④ 身体拘束等の適正化のための研修実施
⑤ 専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくこと
⑥ 身体拘束等適正化検討委員会の記録を2年間保存(5年間保存が好ましい)
上記①~⑤の要件を全て満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認を行った旨を記録しなければならない(⑥は減算の要件では無い)。
これらが実施されていない場合、速やかに改善計画を行政機関に提出後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を行政機関に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から▲10%減算となってしまうのです。
「身体拘束廃止未実施実施減算」が適用される場合の注意点
事業所として身体拘束廃止に関する取組みを行っていない事実が判明した場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
つまり上記を箇条書きにまとめると、「身体拘束廃止未実施減算」が適用される場合には、以下のような取扱いで減算されるということです。
・減算の適用は身体拘束が発生した場合ではないこと
・基準に規定する措置を講じていないこと
・利用者全員についての所定単位数からの減算であること
また、この事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとなります。
つまり、事業者として一旦、要件を満たさないとなると事業者として「身体拘束廃止未実施減算」の手続きが必要となります。
①速やかに改善計画を都道府県知事に提出すること
②事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する
③事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算
④利用者全員について所定単位数から減算
つまり、 事業者が要件を満たさない場合には、「身体拘束廃止未実施減算」が適用されることとなり、一旦これ適用されてしまうと事業者は「利用者全員について所定単位数の減算が最低3か月間適用される」ということです。
参考までに、以下に【減算の適用例】を記載してみます。

上記【減算の適用例】のとおり、実際に月を当てはめてみると分かりやすいと思います。
・4月・・要件を満たさない事実が判明(運営指導等)、速やかに①の改善計画を都道府県知事に提出
・5月・・③のとおり「事実が生じた月の翌月」から減算開始
・7月・・②のとおり①の改善状況を都道府県知事に報告。この「改善が認められた」場合、はじめて減算終了の方向性となる
・8月・・③のとおり「改善が認められた月」まで減算。ということは、7月に都道府県知事に改善状況の報告がなされ、この報告により「改善が認められた」場合、はじめて減算が終了するということ
【減算の適用例】によると、前述しましたが 一旦これ適用されてしまうと事業者は「利用者全員について所定単位数の減算が最低3か月間適用される」ということが分かります。
また、上記で「最低3か月間適用」と記載しましたが、これは、「都道府県知事に改善状況の報告がなされ、この報告により改善が認められた場合、はじめて減算が終了する」ということなのです。
つまり、 この改善状況の報告が認められないとなると、残念ながら、さらに減算適用期間が長くなるということです。
そう言った意味で、事業者としては「身体拘束廃止未実施減算」に該当しないような手立てを、日頃からしっかりと講じておく必要があるのです。
まとめ
今回のブログのテーマは「要注意です「身体拘束廃止未実施減算」に対する対応ができていますか?」としてブログを書いてみました。
勘違いしやすいのですが「身体拘束廃止未実施減算」は、施設において身体拘束が発生した場合は減算を算定する要件ではないのです。あくまでも「身体拘束廃止に対する措置が講じられていない場合に減算する」ということです。
この点については、本ブログを参考によくよく事業者として対策を講じる必要があるのです。
今回も本ブログをお読みいただき、ありがとうございました。引き続き事例等を交えながら深掘りしたブログを書いていこうと思います。
それでは次回のブログもお楽しみに。
——————————————————————————————
(以下、「身体拘束適正化委員会」議事録サンプル)
——————————————————————————————–
令和7年●●月●●日
▲▲▲事業所
書記 ●● ●●
議事録(身体的拘束適正化委員会)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日時 令和7年●●月●●日(月) 午後1時00分~
場所 ▲▲▲事業所 事務所
参加者 鈴木管理者、佐藤、田中、山田(書記)
内容 過去の事例確認、そして身体拘束を行ってはならないという大原則を確認する
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.現在まで身体拘束と疑われるようなケースは無いか。
現時点、事業所として利用者に対する身体拘束を行ったケースは生じていない。しかし、過去の虐待事例が発生した中で、「職員が利用者の両手首をつかみ上げた」事例が監視カメラ録画によって確認されている。
この事例は、行政機関によって「虐待の疑いあり」、「身体拘束の疑いあり」として、判断されたものであることから、こうした事例であっても「身体拘束」に派生する可能性があることを理解すること。
2.現時点、身体拘束を行う事例が無い場合でも未然防止の観点から考える。
現時点、身体拘束が行われていなければ、事業所として身体拘束を検討しなくても良いというわけではない。身体拘束等の事例が無い場合であっても、事業所全体として、身体拘束等の未然防止の観点から利用者に対する支援状況等を、日頃から細めに確認することが必要である。
3.「身体拘束では」と感じた場合について、その手順について。
意識していない形で、結果として身体拘束を行っていたというような事例が生じた場合には、速やかに本社に報告、そしてその事実を行政機関に報告する手順を徹底することを確認する。
4.身体拘束を安易に考えないこと。
事業者として運営を行ううえで、利用者を生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないというのが大原則です。
また、事業者として、「緊急やむをえない理由」として「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を全て満たし、かつ組織としてそれらの要件の確認を行った場合に、身体拘束が行われるものであるが、この外観上の形式が整っているからといって、安易に身体拘束を実施することがないこと。
5.身体拘束廃止未実施減算が適用とならないよう確認
「身体拘束廃止未実施減算」について、この減算に係る算定要件を確認するとともに、事業所として行わなければならない義務を確認した。
【事業所としての義務】
ア 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこと
イ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない
※緊急やむを得ない理由・・「切迫性」「非代替性」「一時性」
ウ 身体拘束適正化検討委員会(テレビ電話装置利用可)は、少なくとも1年に1回は開催することが必要。その結果について、従業員の周知徹底を図ること
エ 従業員に対し、虐待の防止のための研修を1年1回以上実施すること
オ 上記ア~エについて、措置を適切に実施するための担当者を置くこと
【事業所としての今後の対応】
ア 委員会は年1回以上開催(今回実施済。次回来年●月開催予定)
ウ 虐待防止研修は年1回以上開催(今回実施済。次回来年●月実施予定)
エ 担当者(●●管理者)