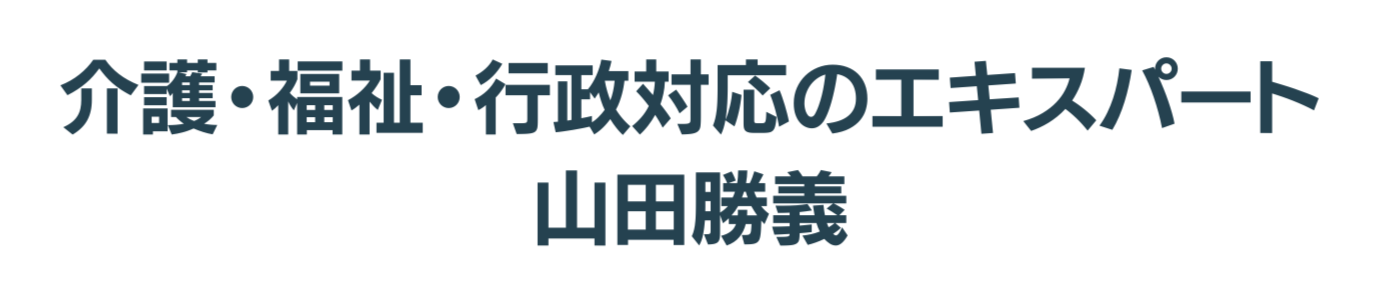模擬運営指導に関わるにあたり、グループホームの運営での人員配置に様々な問題が生じていることが分かってきました。そういった意味で、当面、基本的な部分の確認ができるような内容のブログも書いてみようということで、前回に引き続き、基本的な内容のブログを書いてみます。
さて、グループホームにおいて、従業員のシフトを作成し、また加算を算定するにあたり、以下のような文言が出てきます。
「常勤」、「常勤換算」、「利用者数」、「特定従業者数換算方法」
こうした文言を正しく理解しないと、そもそも基準に合致したシフト表の作成や加算を算定することができないはずです。そして、こうした用語を正しく理解し、事業所運営していかなければ、運営指導等の際、意図しない形で人員配置基準違反となってしまう恐れもあるのです。
今回、こうした基本的な用語を正しく理解し、日頃の業務に生かしていくということが、このブログの目的です。
なお、今回のブログでは、指定障害福祉サービス事業に係る指定基準をベースとし、「東京都」の障害グループホーム事業の内容を参酌します。
では、ひとつひとつの項目は短いですが、こうした「キーワード」を説明していきたいと思います。
「常勤」について
指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等において定められている(就業規則等)常勤の従業者が1週間に勤務すべき時間数に達していることです。
☞ 1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は、32時間を基本とする
「常勤換算」について
事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において、常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業員の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法のことです。
☞ 算出にあたり、小数点以下第2位を切り捨て
☞ 様々な勤務時間の職員が存在する場合、常勤換算により勤務体制を把握できる
★計算例
事業所として就業規則により1週間に勤務すべき時間を40時間とします。
①職員Aの1週間の勤務時間 20時間
②職員Bの1週間の勤務時間 25時間
③職員Cの1週間の勤務時間 15時間
④職員Dの1週間の勤務時間 40時間
⑤職員Eの1週間の勤務時間 32時間
上記①~⑤を合算すると「132時間」です。
この「132時間」を40時間で割ると、「3.3」です。
つまり、この事業所の常勤換算の人数は「3.3人」ということになります。
「利用者数」について
指定障害福祉サービスにおいて、報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「利用者数」は、当該年度の前年度の平均を用いることとなっています。
この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ人数を当該前年度の開所日数で除して得た数とします。
☞ この「前年度」とは、「毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度
☞ 算出にあたり、小数点以下第2位を切り上げ
☞ 算定にあたり、 入所した日を含み、退所した日は含まない
☞ 新規開設、又は再開の場合は推定数による(新規開設等については詳細割愛)
★計算例
事業所として前年度の全利用者の延べ人数を1400人、開所日数を360日とします。
1400人÷360日=3.9人(小数点以下第2位を切り上げ)
つまり、報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「利用者数」は、当該年度の前年度の平均を用いることとなっています。
よって、この事業所で報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数は 「3.9人」ということになります。
「特定従業者数換算方法」について
この「特定従業者数換算方法」については、「人員配置体制加算」を算定する場合に利用します。
この「人員配置体制加算」について、指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人及び生活支援員の人数に加え、利用者数に応じて、一定数の世話人及び生活支援員を加えた場合に算定できるが、この算定に当たっては、「特定従業者数換算方法」を用いることとなっています。
「特定従業者数換算方法」とは、当該事業所において従事する世話人及び生活支援員、当該加算を算定するにあたり加配する世話人及び生活支援員の勤務延べ時間数を、それぞれ「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40時間」で除することにより、当該加算の算定に当たり従業者数の員数に換算する方法を言います。
☞ 算出にあたり、小数点以下第2位を切り捨て
☞ 従業者の勤務時間に最低限確保すべき程度の休憩時間を含む
★計算例
利用者数を15人(区分6が5人、区分5が4人、区分4が6人)とし、事業所における常勤職員の1週間に勤務すべき時間を40時間とします。
この場合、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するために確保すべき勤務の延べ時間数は以下のとおりとなります。
(1)「基準」上置くべき世話人及び生活支援員の時間数
ア 世話人
・40時間×(15人÷6)人=100時間
イ 生活支援員
・区分6 40時間×(5÷2.5)=80時間
・区分5 40時間×(4÷4)=40時間
・区分4 40時間×(6÷6)=40時間
ア+イ=260時間・・・①
(2)「人員配置体制加算(Ⅰ)」を算定に当たり加配すべき世話人及び生活支援員の時間数
・40時間×(15人÷12)人=50時間・・・②
・①+②=310時間
上記、(1)、(2)により、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するためには、世話人及び生活支援員の勤務の延べ合計310時間以上確保することが必要となります。
なお、この「人員体制加算」が生じた理由には以下の3点にあります。この「特定従業者数換算方法」が採用された趣旨を以下①~③に記載します。
こうした制度趣旨を理解すると、こうした計算方法の理解が進みます。
★「特定従業者数換算方法」が採用された趣旨について
①令和3年度報酬における世話人の配置には、「4:1」、「5:1」、「6:1」が存在したが、これが令和6年度報酬における世話人の配置が、「6:1」に一本化された。今回の報酬改定以前の多くの事業所は世話人の配置を「4:1」、「5:1」としており、今回世話人の配置が、「6:1」に一本化されることにより、報酬の減額の補填という趣旨。
②上記のとおり、改定以前の多くの事業所は世話人の配置を「4:1」、「5:1」としており、今回世話人の配置が、「6:1」に一本化されたが、実際に事業所に勤務する人員(世話人、生活支援員)の評価を行ったという趣旨。
③この「人員体制加算」常勤換算法のみであるとすると、就業規則上「(ⅰ)1週間に勤務すべき時間を40時間の事業所」、「(ⅱ)1週間に勤務すべき時間を32時間の事業所」とを比較すると、(ⅰ)の事業所は、(ⅱ)の事業所と比較し、常勤換算1人あたり1週間に勤務すべき労働時間が「8時間」多いにも関わらず、報酬が同じであるという不合理が生じるのです。よって、今回「人員体制加算」の算定にあたっては、この「特定従業者数換算方法」が利用されることになったのです。
まとめ
今回のブログでは、「報酬上満たすべき従業員数の算定方法、加算の算定方法を理解していますか?」というテーマでブログを書いてみました。
これは、グループホーム運営において、基準に従い、基本的な部分の確認が必要であると考えたからなのです。
実は模擬運営指導に関わるにあたり、グループホームの経営者等の方々が、意外とこうした「基本的な部分を理解していない」ことが分かりました。例えば、こうした事業所の人員シフト作成にあたっての基本的な事項や加算算定にあたっての人員配置等の理解が不足している場合があるのです。
特に、今回の令和6年度の報酬改定では、世話人の配置が、「6:1」に一本化されたことにより、事業所として「人員体制加算」を算定することが、安定した事業運営を行ううえで必要となりました。この「人員体制加算」を算定するためには、この「特定従業者数換算方法」を理解しなければなりません。
今回のブログでも前述しました、事業運営を行ううえで、以下の事項を把握することが必要です。
指定障害福祉サービスにおいて、報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「利用者数」は、当該年度の前年度の平均を用いることとなっています。
つまり、こうした「利用者数」は、当該年度の前年度の平均を用いることから、次年度以降も、事業所として、この「利用者数」を把握しておくことが必要です。
今後、障害福祉サービス事業者として、業界団体全体でレベルを上げていかなければ、この業界に参入したにも関わらず、事業継続もままならないというような不幸な事態になってしまう可能性もあるのです。
本日もブログをお読みいただき、ありがとうございました。
——————————————————–
★障害福祉サービスの運営を行っている事業者の皆さま(お知らせ)
私からのお知らせです。
現在、障害福祉サービス事業を行っている事業所の皆様に向けて「模擬運営指導」というサービスを提供開始しました。お蔭様で、すでに数多くの事業者のからもお申込みを頂いております。
障害福祉サービス事業を行う皆様で「運営指導の対応が心配だ」、「書類の準備状況が不安だ」という方々にピッタリのサービスです。
この「模擬運営指導」は、介護・障害福祉分野において、過去約20年間に渡り、約400件以上も運営指導・監査対応を行った税理士・行政書士の山田勝義が「運営指導対策用特別テキスト」に基づき、皆さんの事業所にお邪魔し、「行政担当者の目線」から人員体制の状況、基本報酬や加算の算定状況をはじめとする運営状況全般、書類整備状況等を確認します。
また、模擬運営指導終了後、「模擬運営指導の結果」として改善が必要事項を報告書として取り纏め、お渡しします。
☞ なお、模擬運営指導を受けた事業者の方には、この「運営指導用特別テキスト」をお渡しします。
「自分の事業所でも、この模擬運営指導のサービスを受けてみたい」という事業者の皆さまは、以下のホームページより、お申込みください。