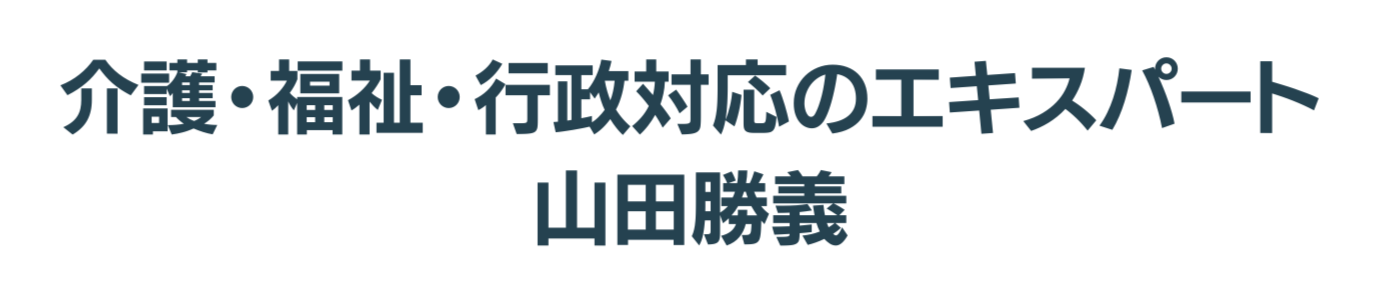皆さん、こんにちは、税理士・行政書士の山田勝義です。
今回のブログでは、介護サービスとして初めて「2025年(令和7年度)最新版 災害・緊急時に備える業務継続計画(BCP)の基本と実践を開催しました【第1回】」という題名でブログを書きたいと思います。
また、私が介護サービス等について、以下の「5つの理由」からブログを書いています。
★5つの理由
①介護サービス(特定施設入居者生活介護)の研修担当となったこと
②上記により介護サービスの事業者の皆さまに研修を提供することになったこと
③介護サービスの、こうした研修やブログが圧倒的に少ないこと
④私の行政担当であった知見を通じ、適切に事業運営して欲しいこと
⑤介護サービスの事業者の皆さんを応援したいこと
特に、今回の業務継続計画(BCP)に関する研修について、介護サービス事業者の皆さまは、事業運営を行ううえで、これらを行うことが「法定」とされています。つまり、これらを事業所として実施していなければ、運営指導の指摘事項となり、かつ業務継続計画未策定減算となります。
こうしたことから、今後、この業務継続計画(BCP)に関する研修についてのブログを定期的にアップして行こうと思います。
また、このブログの内容に留まらず、最新の介護サービスの事業所の現場における虐待の事例、運営指導・監査の事例や報酬改定の動向等についても言及、事業者が注意すべき有用な事項をお伝えすることができればと思います。
では、早速、事業者として確認しなければならない事項をまとめましたので、一緒に確認していきましょう。
業務継続計画(BCP)の目的をしっかりと確認しよう
まず基準において、事業者として業務継続計画(BCP)を行わなければならないのか、その根拠を確認しましょう。
(業務継続計画の策定)
第30条の2 ※各介護サービスが当該条項を準用しています
指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2指定訪問介護事業者は、訪問介護員等(従業者)に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の変更を行うものとする。
では、根拠は理解したとしましょう。次に、事業者の皆さんに質問します。
そもそも事業者の皆さんが、この業務継続(BCP)今回研修を受講する目的は、次の回答例を選んでください。
★回答例
ア 非常災害発生時、利用者や従業員の安全を確保し、事業運営が継続できるため。
イ BCPの研修受講は、運営指導で確認され、また報酬減算となるため。
正しい回答は「ア」です。
では、それを前提として、業務継続計画(BCP)に対する事業所としての考え方を以下に示します。
★事業者が事業継続計画(BCP)に対する考え方とは・・・
①事業所に求められていること・・・
BCPを策定、これを適切に運用を行い、必要に応じて見直しを行うこと。
②BCPの目的とは・・・
非常災害発生時、利用者や従業員の安全を確保し、事業所運営が継続できるようにするため。
③なぜ、運営指導で確認され、報酬減算となるのか・・・
つまり、この「BCPが重要だから」。そのため、上記②の状態が準備できているか確認するため。
上記、これらのとおり事業者として業務継続計画(BCP)を、なぜ行わなければならないのか、その根拠と義務、業務継続計画(BCP)の目的を確認することができたと思います。
では、次に事業者として、これらの義務を果たしていない場合に「業務継続計画未策定減算」となってしまうわけですが、どのような算定要件に該当すると減算となってしまうのでしょうか。
この点について確認してみましょう。
「業務継続計画未実施減算」の算定要件等について確認する
事業者にとって業務継続計画として確認しなければならないことは、この「業務継続計画未策定減算」は、介護サービス事業所として運営指導(実地指導)での最重要チェックポイントです。
この「業務継続計画未策定減算」が適用される介護サービスは、ほとんどが対象となっています。
私が、こうした研修を開催していると、よく他の事業者から運営基準改正をはじめとする法的な根拠の説明ばかりでストレスがあるという話を伺います。こうしたことから、このブログでは事業者が手っ取り早く事業所として対応することだけお伝えします。
次項以下の事業者として対応することに伴い、少なくとも、事業所として運営指導において、現時点で「業務継続計画未策定減算」に引っ掛かることはありません。
すでに「業務継続計画未実施減算」が適用開始されており、運営指導の際、事業所として対応していないと減算対応ということになってしまいます。
では、こうしたことから根拠、単位数・算定要件等について、改めて確認しておきましょう。
★業務継続計画未実施減算 ※特定施設入居者生活介護の場合
所定単位数の3/100に相当する単位数を所定単位数から減算
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。
★事業所として対応する事項
以下の基準に適合していない場合、減算となる。
ア 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画(BCP))を策定すること。
イ 当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずること。
繰り返しとなりますが、この「業務継続計画未実施減算」について、事業者が特に注意しなければならないことは、算定要件ア、イが事業者として対応できていない場合、事業所として利用者全員に減算が適用されるということです。
「業務継続計画未実施減算」を回避するために事業者が行うべきこと
前述のとおり、「業務継続計画未実施減算」が適用される場合、基準に規定する措置を講じていない場合、利用者全員について所定単位数から減算されるのです。
前項の「事業所として対応する事項」において、「BCPの策定」、「必要な措置」と記載されていますが、これでは事業者として具体的に減算回避するために「何をしなければならないのか」が分かりません。
よって、ここで具体的な項目を「箇条書き」でまとめると以下のとおりとなります。
★事業所として減算を回避する項目
① BCP(感染症発生・非常災害発生)を策定すること
② BCPに従い、従業者に対し研修及び訓練を実施すること
・他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない
・全ての従業員が参加できるようにすることが望ましい
・BCPの具体的内容を従業者に共有する
・新規採用時には別に研修を実施することが望ましい
・定期的な教育(研修・訓練)を開催(年1回以上)する
・「感染症のBCPの研修・訓練」と「感染症の予防及びまん延の防止研修・訓練」を一体的に実施することも差し支えない
・訓練の実施は、机上を含め実施手法は問わない
★もっと分かりやすく事業者としてやらなければならないこと
①BCP(感染症発生・非常災害発生)を「策定」すること
②従業者に対し年1回以上の「研修」及び「訓練」を実施すること
③具体的内容を「従業者に共有」すること
★研修の目的をしっかりと理解しよう
①BCPの目的は、自然災害・感染症が発生した場合にどのように事業運営を継続するかということ
☞感染症等の発生後の対応のこと!
②感染症予防及びまん延防止の目的は、感染症を発生しないような取組みを行うこと
☞感染症等の発生前の対応のこと!
上記の研修や訓練は一緒に行うことも可能であるが、記録は分けて記載すること!
このように事業者として「業務継続計画未実施減算」を回避するための行うべきことは分かりました。しかしながら、他の減算項目含め、事業者には行わなければならない研修等が数多くあるのも事実です。
次項では、事業者として「業務継続計画未実施減算」を回避する項目を行いつつ、事業者としていかに業務効率を上げるのかについて説明します。
業務継続計画(BCP)に関する取組みを行うにあたり業務効率を上げよう
前項に引き続き、事業者として「業務継続計画未実施減算」を回避しつつ、いかに業務効率を上げるのかについて考えてみたいと思います。
★業務効率を上げるために行うこと(効率的にやろう・・)
①「研修」及び「訓練」を、他のサービス事業者と連携し行うこと
☞例えば、同一法人内の他の事業所と合同で実施するような場合を想定する
②「感染症のBCPの研修・訓練」と「感染症の予防及びまん延の防止研修・訓練」を一緒に(まとめて)行うこと
☞こうした形で各種研修を一体的に行わなければ、「研修だらけ」になってしまう
☞感染症の発生の「前後」を理解し、研修・訓練の趣旨を誤らないこと
③上記②を行う場合、記録を明確に分けて記載すること
☞感染症の発生の「前後」を踏まえ、それぞれ「分けて」記録していない場合、運営指導で研修・訓練したと認めてもらえない可能性もある
このように、研修や訓練、記録を行うことにより、業務効率を上げつつ、運営指導での指摘事項や業務継続計画未実施減算を受けるようなことはありません。
事業所として、是非こうした事項が対応できているか、今一度、確認・対応しましょう。
現時点BCPを作成していない場合【緊急】※もしくは新規指定申請の事業者
前項まで、事業者が減算を回避する方法を明示しました。
しかしながら現時点BCP(感染症発生・非常災害発生)を策定していない場合、事業者にとって非常にリスクがある状況と言えます。よって、この場合、「急いでBCPを作成」しましょう。
取り急ぎ、以下【図1】の厚生労働省のサイトにアクセスし、自分の事業所類型に沿った「ひな形」を基に、BCPを作成してみましょう。
なお、コンサルタント等にわざわざ高額な委託料を支払い、事業継続計画(BCP)を作成してもらう必要などありません。まずは以下のサイトにアクセスし、自分で作成してみましょう。
【図1】

また、業務継続計画(BCP)の作成にあたり、介護サービスごとに用意された上記【図1】のようなひな形に加えて、厚生労働省では【図2】のような業務継続ガイドラインも発出されているので、作成にあたり参考にしましょう。
★業務継続ガイドライン
①自然災害発生時
②感染症発生時
【図2】


BCP(自然災害発生時)作成にあたっての確認事項
私の開催する業務継続計画(BCP)の研修では、具体的事例(自然災害発生時)を用い、訓練を想定した一体型の研修を開催していますが、今回はそのスペースが無いので、取り急ぎ、自然災害発生時に業務継続するうえで、予め準備が必要な項目を示します。
BCP(自然災害発生時)作成・更新にあたり、次の項目を参考にしてください。
【確認事項】
①BCP(自然災害発生時)の内容
・サービスの継続
・利用者の安全確保
・職員の安全確保
②ハザードマップの確認(事業所のエリアを確認)
・地震ハザードマップ
・津波ハザードマップ
・土砂災害ハザードマップ
・水害ハザードマップ
☞施設が洪水リスクエリアにある場合、高台への避難ルートを確認
③優先する業務
・業務に優先順位をつける
☞避難誘導、利用者の安否確認、緊急連絡網の運用を優先
・利用者の生命に影響を及ばさない業務については、場合によっては一時休止を検討
・その他の事業は業務を縮小して継続
④運営を継続するにあたっての確認事項
・電気が停止した場合の対応
☞停電時に優先する業務(例:医療機器の稼働継続)をリスト化
・水道が止まった場合の対応(飲料水・生活用水)
・通信手段が遮断された場合の対応
・各種システムが停止した場合の対応
・衛生面の対策(トイレ対策・汚物対策)
・必要備品の備蓄
・職員のシフト調整
・他施設との連携
BCP(感染症発生時)作成にあたっての確認事項
私の開催する業務継続計画(BCP)の研修では、具体的事例(感染症発生時)を用い、訓練を想定した一体型の研修を開催していますが、今回はそのスペースが無いので、取り急ぎ、感染症発生時に業務継続するうえで、予め準備が必要な項目を示します。
BCP(感染症発生時)作成・更新にあたり、次の項目を参考にしてください。
【確認事項】
①BCP(感染症発生時)の内容
・サービスの継続
・利用者の安全確保
・職員の安全確保
②基本的な感染対策の徹底
・利用者、職員の健康管理を実施し記録(モニタリングの実施)
・ソーシャルディスタンスを保ち、マスクを着用
・入口に消毒液を置き、施設内に入る時は職員全員が手指の消毒を行う
・定期的にテーブル、手摺、ドアノブ等、多くの人が触れる箇所の消毒を行う
②基本的な感染対策の徹底
・窓開け、機械換気などで換気を行う
・不要不急な会議、研修、出張は中止、延期
・施設への立入りは、体温を計測し、発熱や咳などを確認、記録を残す
・個人防護具、消毒剤等の在庫量・保管場所を確認(最低3カ月分)
③感染症が発生した場合
・利用者、自分の体調不良含め、管理者に速やかに連絡
・速やかに医療機関に受診、医療機関と連携
・法人として情報共有のうえ、必要に応じて行政機関(指定権者・保健所)へ連絡
・利用者等の家族への連絡
④濃厚接触者、感染が疑われる利用者への対応
・個室による管理
・濃厚接触者の特定
・感染、非感染利用者の対応職員の区別
・保健所の指示を受ける
・医療機関受診/施設内での検体採取
・体調不良者の確認
・生活空間、導線の区別
・職員の自宅待機
⑤消毒・清掃等の実施
・当該入所者の居室、利用した共有スペースの消毒・清掃
・手袋を着用、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム液で清拭
⑥介護サービスの内容変更
入浴介護を全て中止。「入居者の生命に影響があるサービスのみ」に介護サービスを集約。
☞食事提供、排泄介助、医療的ケアなど、利用者の生活に直結する業務を優先。
☞感染者発生時に最小限の職員で対応できるよう、業務フローを簡略化
「BCP(自然災害・感染症)における研修と訓練の実施記録」についての議事録を掲載します。
私のクライアントの皆様の事業所では、すでに私からの資料提供のもと、「BCP(自然災害・感染症)における研修と訓練の実施記録」を継続的に実施しています。
反面、「どのような研修を実施し、訓練を行えばよいのか」という質問をよく受けるのです。
こうしたことから、実際に私が主導、開催した「BCP(自然災害・感染症)における研修と訓練の実施記録」における議事録を以下のとおりお示しいたします。
これは私たちが当該委員会で議論した内容をお示しすることにより、多くの介護サービス事業者の皆さんが、こうした研修や訓練行ううえでの「呼び水」になることが目的です。
では、その資料を以下に示します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
令和7年●●月●●日
▲▲▲事業所
書記 ●● ●●
BCP(自然災害・感染症)における研修と訓練の実施記録
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日時 令和7年●●月●●日(月) 午後1時00分~
場所 ▲▲▲事業所 事務所
参加者 鈴木管理者、佐藤、田中、山田(書記)
内容 BCP(自然災害・感染症)における研修と訓練の実施
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ⅰ 研修受講
※「自然災害・感染症が発生した場合、事業継続を如何に行うのか」という視点!
1.BCP(自然災害)の研修受講しての理解・確認(以下①~④を必ず議論すること)
①BCPの必要性は何か(確認)
②基準において事業所が定められている義務を確認する(減算あり)
③BCP作成にあたっての確認事項(事業継続を行うため)
④事業所として予め確認する事項(ハザードマップ、食料・飲料水、消耗品等)
2.BCP(感染症)の研修受講しての理解・確認(以下①~④を必ず議論すること)
①BCPの必要性は何か(確認)
②基準において事業所が定められている義務を確認する(減算あり)
③BCP作成にあたっての確認事項(事業継続を行うため)
④事業所として予め確認する事項(感染対策、感染が拡大した場合の対応)
Ⅱ 机上訓練
※今回の研修での事例をもとに机上訓練を実施のこと!
1.BCP(自然災害)の机上訓練の実施・確認(以下①~③を必ず議論すること)
①巨大地震が発生した場合に利用者の避難誘導はどうするのか(ハザードマップ)
②食料・飲料水、消耗品の備蓄状況確認
③事業所としてのサービス内容のあり方(どのように事業継続するのか)
2.BCP(感染症)の机上訓練の実施・確認(以下①~③を必ず議論すること)
※今回の研修での感染症発生の事例をもとに机上訓練を実施のこと!
①施設における感染予防対策をどのように講じているのか(ハザードマップ)
②感染症が発生・拡大した場合の施設における対応
③事業所としてのサービス内容のあり方(どのように事業継続するのか)
Ⅲ 事業所としての義務(確認)
事業者として、非常災害時・感染症発生時に利用者の安全を図り、「業務継続計画未策定減算」の適用を受けないためにも、以下の①~③の事項の実施状況について確認した。
★BCPについて事業者として必ず行うこと
①BCP(感染症発生・非常災害発生)を「策定」すること
②従業者に対し年1回以上の「研修」及び「訓練」を実施すること
③具体的内容を従業者に共有すること
以上
—————————————————————————————————–
まとめ
今回のブログのテーマは、介護サービス事業者の皆さん向けに初めて「2025年(令和7年度)最新版 災害・緊急時に備える業務継続計画(BCP)の基本と実践を開催しました【第1回】」として書いてみました。
今後も、介護サービスに係るブログについて、運営指導、監査等をはじめ、介護サービスの事業全般に係る有用な情報を書いてまいります。
また、今後もこの「業務継続計画(BCP)」に関するブログをアップし、その内容を提示していきます。
今回も本ブログをお読みいただき、ありがとうございました。引き続き事例等を交えながら深掘りしたブログを書いていこうと思います。
それでは次回のブログもお楽しみに。